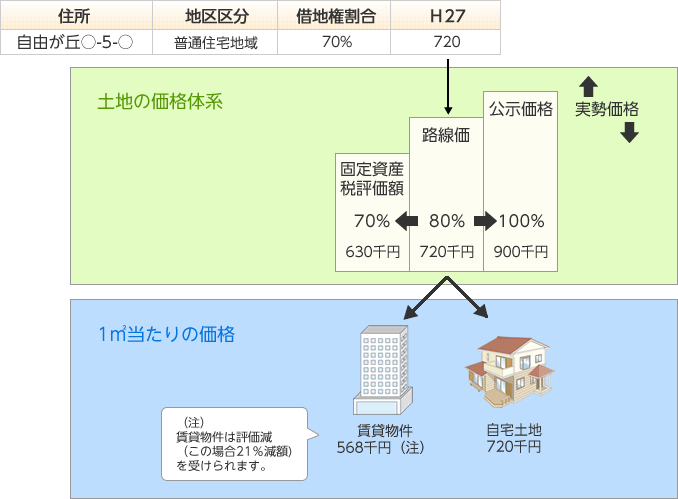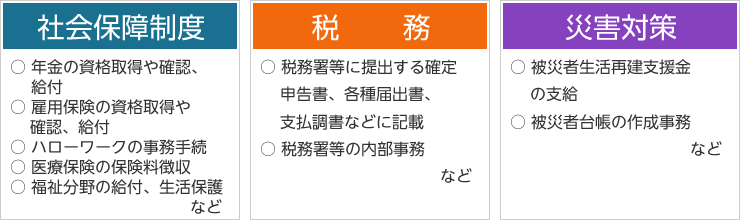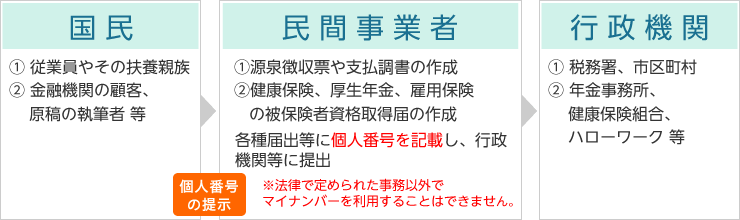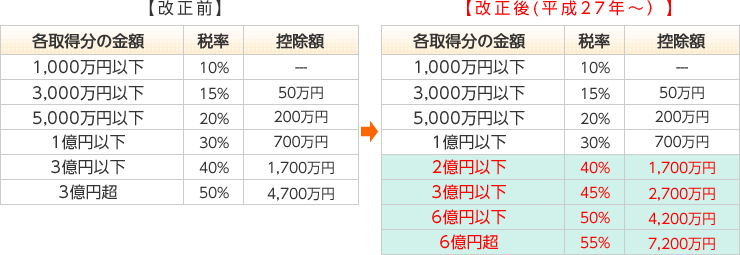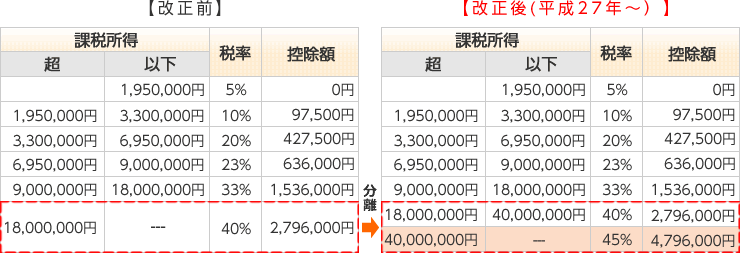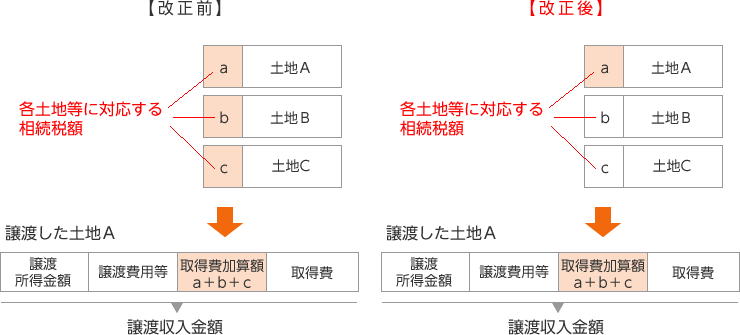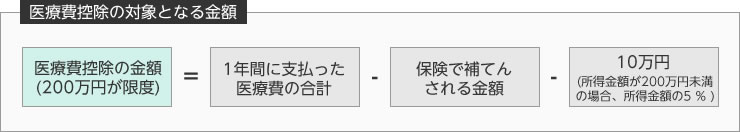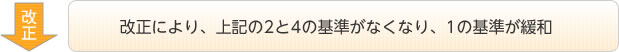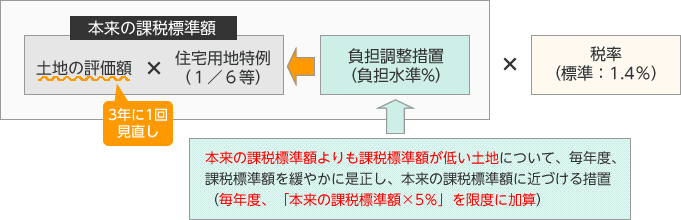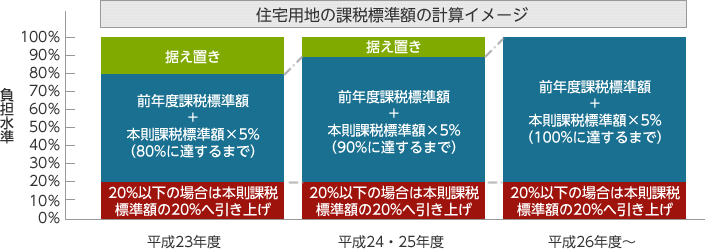平成27年分の路線価の公表
平成27年7月1日に国税庁から平成27年分の路線価や評価倍率が公表されました。今年度の全国平均は前年比-0.4%と7年連続下落していますが、東京・大阪・名古屋の3大都市では、外国人観光客の増加や再開発等の理由により昨年に続いて上昇しています。
路線価の公表
平成27年7月1日に路線価が公表されました。10都道府県で路線価が上昇しており、前年より上昇している都道府県は下記のとおりとなっております。
- 【上昇率1%以上の都道府県】
- 宮城、福島、東京、愛知
- 【上昇率1%未満の都道府県】
- 埼玉、千葉、神奈川、京都、大阪、沖縄
地方でも、宮城県(+2.5%、全国1位)や福島県(+2.3%、全国2位)が東日本大震災による住宅供給の高まりなどから上昇している一方で、秋田県(-4.6%、全国ワースト)では人口減少や高齢化が進むなど2極化が進んでいます。
路線価とは
土地の価格は一物多価と言われています。あるひとつの土地でも、利用目的ごとに様々な価格、実勢価格・公示価格・路線価・固定資産税評価額などがあります。その中で、路線価とは、宅地の相続や贈与の際、その宅地の価格の計算(評価)に用いられる1㎡当たりの評価額をいいます。
路線価